徒然日記からの抜粋です。
2008年
・ハムフェアに行ってきた
今年はクラブブースで買い物をしました。
購入したのはこれ。

A1 CLUBの「切手サイズキーヤーμF675」本体キットと外部実装部品セットⅡ。各\1,000で、合計\2,000なり。
A1 CLUBのメーリングリストでも話題になっていた、切手サイズのキーヤーキットです。
メーリングリストで話題になっていたから、購入したのですが(笑)
「またキーヤーかよ!」と言われてしまいそうですね(先週もキーヤーを作ったばかり)
1608サイズのチップ部品を使用し、PICマイコンはSO8の12F675を使用しています。
このサイズの半田付けなら、腕が鳴りますね(笑)
まあ、組み立てた後、何に使おうか考えていないのですが・・・(汗)
・切手サイズキーヤー組み立て
8月23日のハムフェアで購入した、「切手サイズキーヤーμF675」を組み立てました。
これ、1608サイズのチップ部品を使用したキットなので、それなりの工具がないと、組み立てが大変です。
で、使ったのはこんな工具。

0.3mmのハンダと、チップ部品がつまみやすいピンセット(HOZANのP-891)、温度調節のできるハンダごてHAKKO936。

ハンダごての先は、ナイフ型。
ハンダごての先は、ナイフ型になっているのが好きなのです。
先の部分で、細かい部分のハンダ付け。
面積の広い部分で、チップ部品の両端を温めて取り外したり、DIP部品のハンダ、それと線材の予備ハンダ。
これ1本でどちらでも使えるので、便利だと思うんですけどね~。
慣れない人は使いにくいらしい。
ただ、これにも欠点があって、チップ部品が密集している部分では、コテ先が入らない時がある。
そんなときは、先の細いものと交換して使用しています。
ちなみに、0.3mmハンダはこんなに細いです。
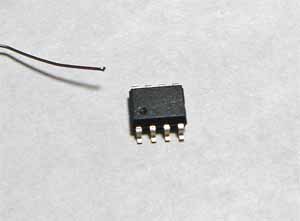
SO8のPICマイコンと比較。
このくらいハンダが細いと、チップ部品のハンダ付けも楽です。
ちょっと面積が広いと、ハンダをかなり流し込むことになりますが・・・。
で、ハンダ付けを開始。
PICマイコンから取り付けて、周辺に広がる形で部品を取り付けます。
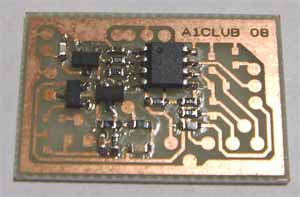
ハンダ付け中。PICマイコン→抵抗・コンデンサ→トランジスタ→抵抗・コンデンサという順序で取り付けているところ。
写真でも分かると思うのですが、基板の表面が少し酸化しています。
フラックスで保護してあるらしいのですが、さすがに時間が経っているので、基板にハンダが乗らず苦労しました。
あと、チップ抵抗の下などにパターンが走っているので、ちょっと気を遣いました。
そのパターンにハンダを乗せちゃうと、部品がハンダ付けしにくくなるし、部品がちょっとずれると、部品とパターンがショートしちゃうし・・・。
レジスト付きの基板なら、気にならないのですが。
キットの性質上、仕方のないことですよね。
で、50分ほどで部品取り付け完了です。
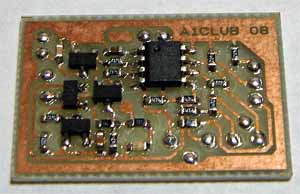
できあがりの様子。
線材を取り付ける場所にも、酸化防止のために、ハンダを盛っておきました。
あと、フラックスが気になるのですが、洗浄してしまうと、パターンの銅箔を保護する物がなくなるので、このままの状態にしてあります。
で、まだ動作確認をしていません。
ケースに組み込んでから動かそうと思って・・・。
さて、ケースをどんな感じにしようかな~。
・ケース加工な一日
まずは、切手サイズキーヤー用のケース加工。
キットは、8月23日にハムフェアで購入し、部品実装だけは9月7日に終了していました。
それを入れるためのケース加工です。
使用するケースは、タカチのYM-65。
こんな感じで部品配置をします。
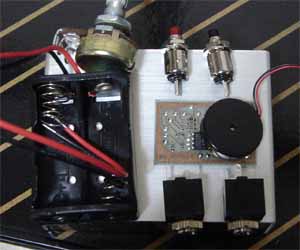
電池ケースは単五用です。これで、ケースの大きさが分かるでしょ?
配置が決まったら、穴を開ける場所をポンチで凹ませ、ドリルで穴を開けます。

いつものように穴あけ加工中。
今回は、なかなか上手く穴あけができました。

電池ケースとプリント基板は、両面テープで接着します。
あ、ボリュームの柄が長かったので、これも5mmほど切り詰めています。
穴あけ加工ができたので、来週あたり、内部配線を行う予定です。
ああ、早く動かしたいなぁ。
この大きさのエレキーなら、FT-817NDにもピッタリですね。
で、小型のパドルが欲しくなると(笑)
・切手サイズキーヤー完成
先週末ケース加工を行った、切手サイズキーヤーの組み込みを行いました。

組み込み中・・・って、組み込み終わってますが(汗)
小型にしようとしたので、なかなか難儀しました。
特に、電池ケースとボリューム部分のスペースが少なく、あと、ケースのふたを止めるネジが予想以上に長かったのが辛かった。
で、こんな感じに組み込みました。

電池ケースの中にあるのは、ブザーです。
ブザーは、カバーに開けた穴に合わせて貼り付けるようにしています。
ボリュームは、もう少し外側に持って行けるのですが、電池ケースから出ている線材を避けるためにこの位置になっています。
小型にしたといっても、無理やり詰め込むのは好きではないので、オーソドックスな感じになってしまいました。
結線に間違いがないのを確認し、テスタでショートチェックを行い、電源を投入します。
・・・おおっ!「QRV」のモールス音が聞こえましたよ(嬉)
で、おもむろにパドルを接続し、モールスを送信してみます。

しっかり動作しました。
LEDも実装しているので、キーイング中はブザーとLEDで確認できます。
まあ、LEDはカバーを取り付けると見えなくなってしまいますが・・・。
で、動作をさせていて思ったのですが、やはり電源スイッチが欲しい。
「低消費電力だから無くてもいいかな?」と思っていたのですが、このキーヤー、「スイッチを押しながら電源ON」で動作が変わる機能が付いているのよね。
あと、小型にしたためか、持ち運び時にプッシュボタンを押してしまう事が多いし・・・。
で、別冊CQに書いてあった方法を使い、電源スイッチとすることにしました。
それは、無線機との接続側のイヤホンジャックの「リング」と「スリーブ」が接続されると電源ONとする方法。
ステレオジャックにモノラルプラグを挿すと、「リング」と「スリーブ」が接続される事を応用しています。
こうすれば、無線機との接続ケーブルを挿すと電源ON、抜くと電源OFFとする事ができます。
無線機との接続ケーブルを気にする必要がありますが・・・。
一通り動作確認ができたので、カバーを取り付けて完成です。

前面はこんな感じ。プッシュスイッチは、メモリーキーです。

背面はこんな感じ。パドル接続部と、無線機への接続部です。

今回は、なかなかうまくできました。
結局、配線などで4時間ほどかかりました。
で、操作してみて思ったのですが、電源投入時の「QRV」と、メモリ内容が空の時の「NO DATA」は、スピード調節ボリュームとは関係なく、一定のスピードなのね。
最初、それを知らなくて、「あれ・・・ボリュームでスピードが変わらない」と焦ってしまいました(笑)
パドルでキーイングすると、スピードは変わります。
しかし、小さいですね~。

BENCHERのJA-2と比べると、小ささが分かると思います。
あ~、この大きさに合うパドルが欲しくなってきた(笑)
何かいい物はないかな。
で、ここまで小さくできたのも、切手サイズキーヤーの頒布があったからです。
A1 CLUBの皆さんに感謝しないと・・・。
あ、あと、無線機との接続ケーブルを製作しよう。
2009.08.02 |